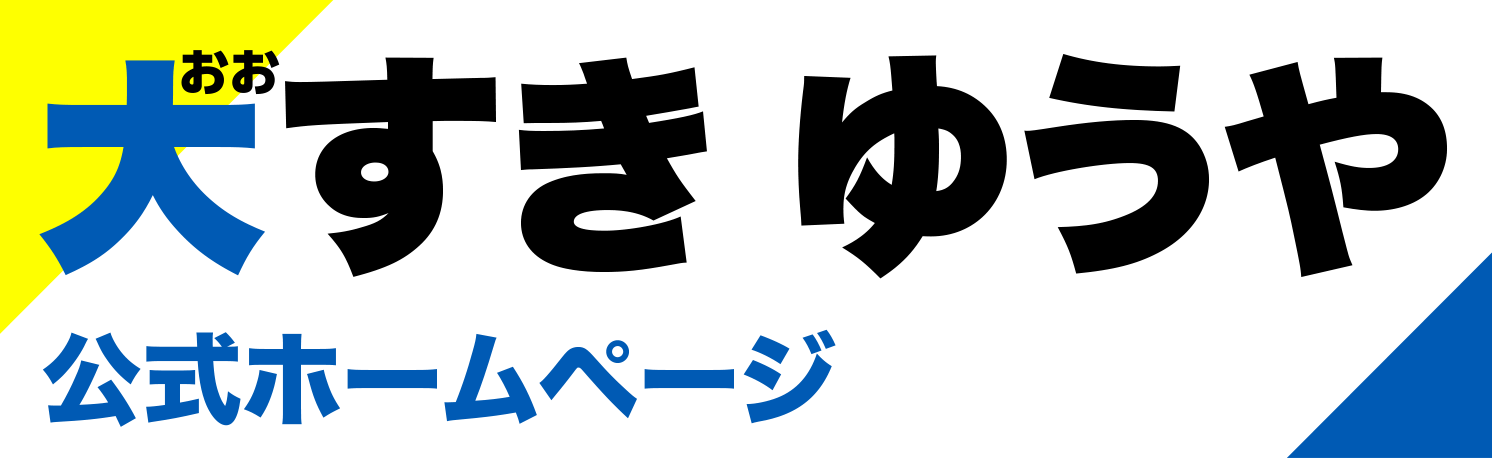②【行財政改革】この先6年間の研究課題!予算を使い切らなければ、次年度の予算が減らされる仕組みは何とかならないのか?公務員へのインセンティブ制度の導入とともに考えて発信します!
2025年参院選千葉選挙区候補者
完全無所属|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです!
選挙戦も最終盤です!!
応援メッセージが続々届いているので、ご紹介です!
~~~~~
柏市30代女性
【応援メッセージ】
初めまして。
メッセージ失礼いたします。
20代の頃は政治や情勢にあまり関心がなく、気が向いた時に選挙へ行くといった人間でした。しかし現在は日本の将来に非常に不安を感じ、今更ではありますが投票権を持っている自覚をきちんと持たなければと思うようになりました。
そこで今回の投票の候補者を調べ、大すきさんのHPにたどり着きました。今までは街頭演説等を聞きに行かなければ政策があまり分からずどの政治家さんを選べばいいのかさっぱりでしたが、大すきさんのHPでは政策が全て書かれており感動しました!説明も分かりやすくて素晴らしいです。また共感する所もとても多くこの政治家さんを応援したい、当選して欲しい思ったのは初めてです!
先ほど期日前投票に行き、大すきさんに投票をしてきました。家族にもHPを紹介し、好感触を得ております。
選挙戦大変とは思いますが最後まで頑張ってください!当選しますように!心から応援しております!!
(追記忘れ)
あとSpotifyも聴いております!漫画家のためいつもラジオを聴きながら仕事をしているので音声配信本当にありがたいです。
選挙活動の詳細も分かりやすく、とても聞きやすいのでこちらも家族に勧めております。暑い日が続いていますので何卒ご自愛ください。
~~~~~
非常に励みになります!!
発信方法も含めてこちらの意図が伝わっており、非常に嬉しく思います!!
もう1つご紹介!!
10代からのメッセージです!!
~~~~~
松戸市10代女性
選挙ポスターから、ブログがあることを知りました!スマホですぐに見ることができ、詳しく知りたい内容もリンクが貼られていることで、すぐに知ることができて非常に効率的だなと感じました。
お忙しいと思いますので、以下は10代の独り言だと思って見ていただけるとありがたいです。
明日、期日前投票に行こうと思っています。私が投票に行く理由は2つあります。1つ目は、(当たり前ですが)18歳の時に得た選挙権を行使するためです。大学で史学を学んでいる身からすれば、過去の人々が必死に戦って得た選挙権です。当たり前に選挙権を得られている今、これを行使するのはむしろ義務だと思います。
2つ目は、社会科の教員志望であるからには、選挙には毎回参加しなければならないと考えているためです。
最近(選挙権が18歳に引き下げられたことで)、周りでも選挙に行くという友だちが増えたと感じます。その一方で、選挙に関心のない友だちもたくさんいます。選挙よりも勉強(テストが近いので…)、選挙よりもバイトといった感じみたいです。これについて、私はすごく危機感を持っています。あれほど授業でも、TVでも、SNSでも大切だと伝えられているのに行かないのかと思うと、もっと政治教育に力を入れる必要があると感じました。(政治的中立な立場を取らなければならないので、少し難しいですが…)2,3年後、教師になった時に、政治に参加することの大切さを理解してもらえるような授業ができるように、今から頑張っていきたいと思います!
以上、10代の選挙への気持ちと、これからの決意でした。長々と稚拙な文章、申し訳ないです。まだ、選挙権を得て1年とちょっとですが、選挙には欠かさず行っていますし、これからも欠かさず行きます!大すきさんの、これからの活躍に期待しています!頑張ってください!
~~~~~
頼もしいメッセージです!!
選挙権って当たり前ではありません!
1945年に法改正があるまで女性には選挙権がありませんでした。
“過去の人々が必死に戦って得た選挙権”
本当にそのとおりです!!
“選挙が大事なのは分かっている!”
“けど、どうやって考えれば良いのか分からない!”
そんな声にお答えして、投票行動の思考過程などをブログで公開しています!
少しでも多くの方々へ選挙に興味を持ってもらえるよう、最後の最後まで周囲の方々へホームページの周知・拡散をよろしくお願いいたします!!
さて、本日の本題②です!
国家も含めた公務員の行財政改革です。
幼少期から思っていた疑問に関する政策課題です。
ただ、他の政策と異なり、まだ私の中で明確化できていない部分もあります。
国家経営を内部から観察して、6年間のうちに提案内容を明確化したいと考えています。
それでは、行きましょう!
私が公務員の行財政に対して幼少期から感じていた疑問
それは、
“今年度中に予算を使い切らなければ、次年度の予算を減らされてしまう”
という慣行です!!
どういう意味か説明します。
例えば、A分野の予算が100で組まれたとします。
それが、実際には90で済んだとします。
そうすると、
“A分野の予算は90あれば十分なんだね!”
という判断により、次年度の予算は90となります。
100の予算が90で済むことは、経営者側にとっては非常にありがたい話です。
他方、現場側としては、
“今年は90で済んだけど、来年も90で済むかは分からない”
“次年度も90でやれるかもしれないけど、やりくりするのは面倒”
という気持ちもあります。
そのため、90で済みそうと思っても100の予算を使い切ります。
“念のため、次年度も100の予算を獲得しておこう!”
という現場側の判断です。
これにより、現場側は、次年度も100の予算を獲得します。
問題の所在は、
“念のため”という不要不急な理由で、
使わなくとも済んだ10の予算が使われた点にあります。
では、どのような改善策が考えられるのでしょうか。
1つは、使わなかった10の予算をA分野の次年度予算に繰り越すという方法です。
例えば、100の予算をもらったA分野が、実際には90で済んだとします。
この場合には、浮いた10の予算を次年度に繰り越します。
次年度のA分野の予算は、100+10(繰り越し分)で、110となります。
現場側は、“念のため”という不合理な理由で、10の支出をする必要がなくなります。
経営者側としても、10の支出が不要不急の事柄に充てられる事態を回避できます。
A分野の現場は、110の予算を使って、少し攻めた活動をするのもありと思います。
また、110の予算で足りないならば、次年度も90で済むように努力して、その次の年度に120の予算で、普段はできない活動をするという判断もあり得ると思います。
現場にとっては創意工夫のモチベーションになりますし、経営者側としても不要不急な支出に充てられる場合と比較して、効果的なお金の使い方を現場に期待することができます。
では、このような柔軟な予算編成は可能なのでしょうか?
はい、可能です!
実は採用している自治体があります。
近年、ばりばりに勢いを感じる地方自治体・・・
それは、
“福岡市”
です。
“枠予算”
という考え方を採用しています(【新しい自治体財政を考える研究会】)。
この考え方を採用するだけでも政界の業務効率化は相当に進行するように思います。
ただ、チームのインセンティブにはなりますが、個人のインセンティブにはなりません。
また、前年度予算の踏襲となると、納税者に歳出削減(減税)の効果を与えられません。
そこで、私は、公務員個人のインセンティブにもなる仕組みを研究したいと考えています。
例えば、Aの分野に100の予算があったとします。
実際には、Aの分野を90の予算で完了したとします。
Aの分野の事業が90の予算で達成できたのであれば、次年度の予算の基本は90です。
これにより、前年度と比較して、10の歳出削減となります。
ただし、歳出削減のみでは現場のモチベーション低下になります。
そこで、前年度の余剰となった10の予算の半分は次年度に繰り越します。
また、残りの半分は、現場のインセンティブとして、支給します。
そうすると、次年度のA分野の予算は95(うち前年の繰り越し5)となります。
現場側の努力により効率化した10のうち半分は個人へ、半分はチームへ還元します。
前年度と比較したときの10の歳出削減は、納税者への還元となります。
個人へのインセンティブ制度がある以上、必然的にA分野の現場には、次年度も業務効率化のモチベーションが発生するはずです。
95の予算を85で達成する可能性もあります。
このように現場のチームと個人のインセンティブを図る仕組みで、行財政を効率化します。
もちろん、インセンティブを追求するあまり、利便性が低下するのは本末転倒です。
インセンティブ制度の創出にあたり、この点をいかにして客観化するかは鍵となります。
“より良いサービスをより効果的・効率的に供給する”
資本主義の原理を福祉主義の現場に適度に浸透できれば、大きな改革となるはずです。
業務効率化による公務員個人へのインセンティブの付与は他にも方法があります。
それは、副業・兼業です。
予算だけでなく、業務の性質によっては、執務時間のインセンティブを図りたいです。
要するに、8時間の仕事を6時間で終わらせられるようになったのであれば、8時間の給料を受け取って、残りの2時間を他の民間需要に充当させるという方法です。
特に地方を中心に高齢化が深刻です(地方の人手不足が深刻です)。
高齢者の足の問題は、地域社会の大きな課題です。
乗合タクシーの運転手やスーパーの買い物回りなど、公的な民間需要は多々あります。
農業に対する労働者人口の供給も公的な民間需要といえるかもしれません。
もちろん、民間需要に対応した労務価値は、民間企業から受け取ります。
公務員個人としては、公務の効率化による公給のインセンティブとともに、民間需要への対応による民間企業からの収入も得られるため、所得の増加を実現できます。
社会的にも少子高齢化に伴う労働者人口の減少という地域課題を解決する意義があります。
千葉県選出の参議院議員となれば、国家経営の現場を直接体感することができます。
また、少なくとも、県内各自治体の経営情報にも触れやすくなるはずです。
少子高齢化に伴う労働者人口の減少という社会問題は、日本社会の大きな課題です。
この先の国政・県政・市政の経営を考えるにあたり、誰に経験を積ませることが得策でしょうか。
少なくとも有権者としての私は、
“大すきゆうやに経験を積ませることが得策”
と考えていますが、本ブログをご覧の“あなた”はいかがでしょうか?
以上
行財政改革について、公務員へのインセンティブ制度とともに考えて発信しました!
~~~~~~~~~~~
個別連絡のできるLINE公式アカウントです!
ご意見・ご感想お待ちしています!
応援メッセージやラジオのトークテーマも大歓迎です!
「期日前投票行って来た!」のご報告も感涙です!!
「10人連れて行って来た!」は大感涙です!!笑
毎日23時からYouTubeを利用した生配信(ライブ)を実施します!
(15分から30分ぐらいを予定しています)
なお、翌日12時頃にホームページの音声配信にもアップ予定です。
ぜひともお楽しみいただけますと幸いです!
お知らせ配信専用のXアカウントです。
みなさまフォローしてご活用お願いします!
<選挙ドットコムからご覧の方へ>
すべての情報は公式ホームページにあり!!
是非ともご来訪ください!!
~~~~~~~~~~~