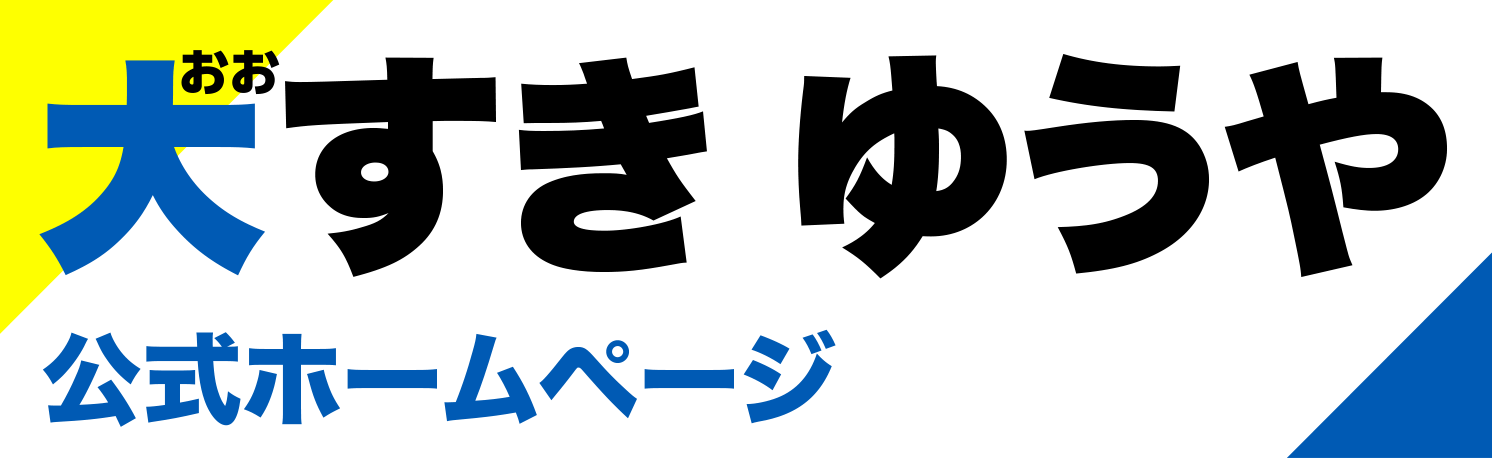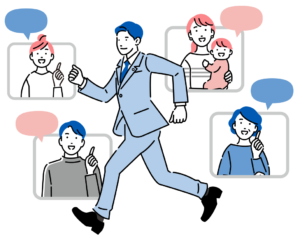②【朝日新聞】各社アンケートを詳細に回答します!
2025年参院選千葉選挙区候補者
千葉・市原出身|完全無所属|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです!
政見放送とともにラジオも好評です!!
ラジオに関する嬉しいメッセージをご紹介します!
~~~~~
柏の葉キャンパス駅は参政党がよく立って演説しています。
自民党、共産党は昔ながらのスタイルで、聞いても頭に残りません。
参政党は、去年あたりは立候補者の話が今っぽさがあって興味を持ちました。
がその後党首の話をネットで読んだりするうち危ない党に見え初めました。
政治家はみんな嘘つきに見える。
そんな時、たいして期待もせずに大すきさんのHPをみて、インターネットラジオを聞きました。
選挙公報ではよく分からなかった部分、ラジオではよく伝わったと思います。
初めて政治家が一人の市民に見えました。
チャレンジしている内容も面白い。
なんだか応援したくなったので、一票入れてきました。
頑張ってください。
~~~~~
ありがとうございます!!!
頑張ります!!!!
ラジオは人柄が伝わる良いメディアなのです!
みなさま是非ともご拝聴ください!!
さて、本日の本題②です!
5月28日に交付、6月6日締切の朝日新聞アンケートです。
読売新聞、毎日新聞と同様に網羅的な選択式です。
交付・締切ともに突出して早かったです。
あまりにも締切が早く、本投稿にて修正の言及も少なからずしています。
コメ問題の設問がないことからも分かるように、1か月あれば色々起こります。
(また、締切後に出馬表明した候補者も多々いますが、どうするのでしょうか)
特徴的なのは、各政党や党首への高感度や連立の在り方に対する質問かなと思います。
最後のマスメディアとインターネット・SNSへの質問も面白いと思いました。
それでは、はりきって行きましょう!
~~~~~
Q1 今回の選挙に際して、あなたが最も重視する政策はどれでしょうか。また2番目、3番目はどうですか。カッコ内に番号を記入してください。
- 外交・安全保障
- 財政・金融
- 産業政策
4.農林漁業
5.教育・子育て
6.年金・医療・介護
7.雇用・就職
8.治安
9.環境
10.政治・行政改革
11.地方分権
12.憲法(護憲・改憲)
13.震災復興・防災
14.社会資本(インフラ整備など)
15.原発・エネルギー政策
16.デジタル政策
17.ジェンダー・家族
18.外国人政策
最も重視する政策
- 政治・行政改革
【詳細な理由】
根本的に行財政改革(歳出の合理化・効率化)へ強い関心があります。資本主義社会を生きていく上で、お金は必要不可欠です。多くの有権者は、命を削ってお金を稼いでいます。お金に真摯に向き合うことは、命に真摯に向き合うことと思います。経営者にとって、金の管理は命の管理です。国家経営者における金の管理の問題は、経営者としての適格性の根幹にかかわる問題です。カネの問題を管理できない組織に国家経営を委ねている有権者の判断には甚だ疑問があります(積極支持層も無関心層も同様と思います)。完全無所属・寄付献金を一切お断りして参議院選挙に参戦していることからも推察いただけるかと思いますが、お金や時間の使い方に対する合理化・効率化の意識は、私の強みの1つです。国家経営を内部から観察したときに、合理化・効率化の余地がどの程度広がっており、それらを合理化・効率化した先に、どのような世界が広がっているのかへ強い興味・関心があります。特に超少子高齢化に伴う労働者人口減少という政策課題との関係で、現役世代の負担軽減と持続可能な社会保障制度の維持を実現する行財政改革(歳出の合理化・効率化)は、重要と考えます。
2番目に重視する政策
- 教育・子育て
【詳細な理由】
少子高齢化に伴う労働者人口の減少はこの国の将来にとって喫緊の課題です。少子化対策としては、子は社会の宝という意識をもって、子を産み・育てるイメージを持ちやすい社会とすることが必要です。具体的には、①義務教育課程の給食費一律無償化(*中学校も可及的速やかに実現すべきです)、②高校教育における実践的教育の充実化(金融、法律、職場体験など)、③高卒市場の自由化(1人1社制の慣行廃止)、④いわゆるFラン大学と呼ばれる私立大学の縮小・廃止、⑤国立大学の学費減免が有効であると考えています(詳しくは、2024年の衆議院選挙で投稿したブログもご参照ください【実践的教育の充実化とは?】・【高卒求人の1人1社制は高卒新卒の足かせではないか?】・【大学全入時代と少子高齢化に伴う労働者人口減少の問題の関係とは?】)。
3番目に重視する政策
6.年金・医療・介護
【詳細な理由】
現役世代の負担を軽減しながら社会保障を維持する政策が、世界的にも類を見ないほど超少子高齢化が進行する日本社会にとっては極めて重要となります。70歳以上の窓口自己負担割合の一律3割負担、OTC類似薬の健康保険からの適用除外、無価値医療の健康保険からの適用除外などによる社会保障費の歳出の合理化・効率化を図り、国民民主党の主張する給与所得者控除等の引き上げにより就労意欲・勤労意欲を高めることが、健康寿命の増進にも繋がるため、持続可能な社会保障制度との関係でも重要と考えます。
Q2 あなたは、次の政党や政治家に対し、好意的な気持ちを持っていますか、それとも反感を持っていますか。好意も反感も持たないときは、下の「感情温度計」で50度としてください。好意的な気持ちがあれば、その強さに応じて51度から100度、また、反感を感じていれば、49度から0度のどこかの数字で答えてください(小数点を用いず、0~100の整数でお願いします)。
① 自民党 (20)度
② 立憲民主党 (40)度
③ 公明党 (25)度
④ 日本維新の会 (40)度
⑤ 共産党 (40)度
⑥ 国民民主党 (40)度
⑦ れいわ新選組 (40)度
⑧ 石破茂 (30)度
⑨ 野田佳彦 (40)度
⑩ 斉藤鉄夫 (35)度
⑪ 吉村洋文 (45)度
⑫ 田村智子 (40)度
⑬ 玉木雄一郎 (40)度
⑭ 山本太郎 (40)度
【詳細な理由】
令和7年6月6日時点の一有権者としての感覚です。
Q3 長期的な方向性として、次の意見についてあなたは賛成ですか、それとも反対ですか。
長期的には…
賛成・やむをえない
どちらかと言えば賛成・やむをえない
どちらとも言えない
どちらかと言えば反対・容認できない
反対・容認できない
①消費税率を10%よりも高くする
反対・容認できない
【詳細な理由】
消費税は消費の多い現役世代の負担が実質的には大きいです。社会保障の財源として、大きな役割を担っていることは否定しませんが、10%が我慢の限界というラインのように思います(財源財源と繰り返し述べる政権与党が政治とカネの問題について具体的な改善策を一切示さない態度からすると、一有権者としては、我慢の限界を超えているというのが正直な気持ちです)。
②年金や医療費の給付を現行の水準よりも抑制する
どちらとも言えない
→どちらかと言えば賛成・やむをえないに訂正します。
【詳細な理由】
1 年金について
どちらかと言えば賛成・やむをえないというより、正直、現行の水準の給付を期待することは、どうにもならないのではないでしょうか。厚生年金の積立金の基礎年金への流用の問題からも明らかなとおり、制度として破綻していることを自認せざるを得ない状況のように思います。年金制度は、現役世代から高齢者世代への「世代と世代の支え合い」(賦課方式)を前提としています(【厚生労働省ホームページ】)。超少子高齢化社会を前提とすると、誰が見ても明らかに公平性ある制度の維持は難しいのではないでしょうか。
給与所得控除等の引き上げにより、就労意欲・勤労意欲を高め、高齢となっても自助を促す政策は、高齢者の認知機能の低下を遅滞させる結果にも繋がりますから、年金給付に依存し過ぎない老後や医療給付などの社会保障費の抑制という観点からも合理的と考えます。
2 医療給付について
現在の日本は、世界的に類を見ないほどの超少子高齢化です。過去の日本と比較して、支える人口に比して、支えられる人口の割合が多いことは明らかですから、社会保障制度の給付水準を引き下げて、現役世代の負担を抑制する必要があります。具体的には、70歳以上の窓口自己負担割合の一律3割負担、OTC類似薬の健康保険からの適用除外、無価値医療の健康保険からの適用除外などによる医療費の歳出削減(推計2~7兆円の医療費削減)が有効です(集英社オンライン2025.2.20【「健康保険料高すぎ!」「もう限界」国民の負担を増やす前に厚労省がやるべき、2~7兆円もの医療費を削減できる3つの医療改革とは】)。
③競争力のない産業・企業に対する保護を現行の水準よりも削減する
賛成・やむをえない
【詳細な理由】
米問題もそうですが、保護主義による政策が奏功していると感じたことがありません。資本主義(自由主義)の領域に対する政府の介入は、公害問題や消費者問題などの福祉主義の要請が働く場面に限るべきと思います。日本社会全体として、超少子高齢化に伴う労働者人口減少の問題は大きな課題です。労働者人口を外国人に頼っているような状況もあるため、産業・企業の淘汰(とうた)が進んでも、労働者が職に困ることは想定し難いです。政府による保護主義の政策は、市場原理における労働者人口の適切な配分を阻害し得る要因です。
④国内で必要な電力は、すべて再生可能エネルギーで発電する
どちらかと言えば賛成・やむをえない
【詳細な理由】
日本のエネルギー自給率は12.6%です(【経済産業庁資源エネルギー庁】)。長期的にみれば、エネルギー自給率を高める再生可能エネルギーを増やしていくことが、国際情勢に左右されない安定的な国家経営にとって重要であることは明らかと考えます。
Q4 次に挙げる意見について、あなたは賛成ですか、それとも反対ですか。
賛成
どちらかと言えば賛成
どちらとも言えない
どちらかと言えば反対
反対
①日本の防衛力はもっと強化すべきだ
どちらかと言えば反対
【詳細な理由】
こちらの投稿もご参照ください(【国家観と財源】司法試験の公法系全受験者2位のイズムを受けた弁護士兼政治家が発信する憲法9条の改憲問題の考え方とは?(アップデートver))。日本らしい国防の在り方を考えても良い時期なのではないかと思います。
防衛力の強化には賛成ですが、いたずらな防衛費の増額には反対です。減税の主張に対しては財源の話を持ち出しますが、防衛費に関しては財源の説明が丁寧になされている印象がなく、政権与党の姿勢には違和感があります。防衛力は強化できるなら強化した方が良いに決まっています。ただ、だからといって、お金を湯水のごとく使って良い訳ではありません。
私は、現在の政権与党である自民党に対して組織的・構造的にお金の使い方に関する強い不信感があります。防衛費は、どちらかといえば、国民生活と縁遠い支出のため、一有権者として、支出の必要性・合理性を感じにくいものです。だからこそ、防衛費の支出に対しては、支出の必要性・合理性が丁寧に説明されなければなりません。にもかかわらず、一有権者としては、現在の政権与党から合理性・説得性・透明性ある説明がなされていないと感じます。個人的には、政治とカネの臭いが強くする分野と感じているのですが、防衛費の強化とともに防衛費の増額を実施するのであれば、歳出の必要性・合理性について、相当に丁寧な説明が必要と考えます。
なお、トランプ政権は、日本を含むアジア太平洋の同盟国に対して、防衛費を国内総生産(GDP)比5%に増やすよう要求しています(2025年6月22日時事通信【防衛費GDP比5%要求 米政権、日本含むアジア同盟国に】)。2022年まで約5兆円で推移していた防衛費ですが、2025年は約8兆7000億円です(2024年12月27日時事通信【防衛費、過去最大8.7兆円】、2022年11月28日日本経済新聞【岸田首相「防衛費GDP2%、27年度に」】)。財源はどうなっているのでしょうか。石破首相は、「日本の防衛費は日本が決めるもの」などと述べていますが、本当に主体的に決定できているのでしょうか(2025年3月15日NHK【米 国防次官候補 公聴会出席“日本の防衛費GDPの3%にすべき”】)。2022年までのように、防衛費を5兆円程度(GDP比1%程度)にまで減らすという姿勢こそが、日本らしい主体的な防衛費の決定のように思いますが、いかがでしょうか。
②日米安保体制は現在より強化すべきだ
どちらかと言えば反対
【詳細な理由】
こちらの投稿をご参照ください(【国家観と財源】司法試験の公法系全受験者2位のイズムを受けた弁護士兼政治家が発信する憲法9条の改憲問題の考え方とは?(アップデートver))。日本らしい国防の在り方を考えても良い時期なのではないかと思います。
③北朝鮮に対しては対話よりも圧力を優先すべきだ
どちらかと言えば反対
【詳細な理由】
こちらの投稿をご参照ください(【国家観と財源】司法試験の公法系全受験者2位のイズムを受けた弁護士兼政治家が発信する憲法9条の改憲問題の考え方とは?(アップデートver))。日本らしい国防の在り方を考えても良い時期なのではないかと思います。
④非核三原則を堅持すべきだ
賛成
【詳細な理由】
私は防衛費を拡張ではなく縮小に向けて進めていくことが日本らしい国防の在り方と考えています(【国家観と財源】司法試験の公法系全受験者2位のイズムを受けた弁護士兼政治家が発信する憲法9条の改憲問題の考え方とは?(アップデートver))。第二次世界大戦における日本が被った核兵器の悲劇を現在の政権与党は忘れてしまったのでしょうか。先の投稿でもお伝えしているように、日本の憲法は米国からの押し付け憲法との評価もありますが、私は特に憲法9条は国家としての理想が詰まった素晴らしい条文であると考えています。時の総理大臣であった自民党の佐藤栄作内閣時に閣議決定された「非核三原則」(核兵器を持たない、作らない、持ち込ませない)は、日本国民として誇れる国策と考えます。しかし、残念ながら、現在の自民党政権には、佐藤栄作内閣時のイズムを感じることはできません。直近の政権交代となった2010年の旧民主党の鳩山由紀夫内閣の調査により、日米間に核持ち込みを容認する「密約」が存在したことを覚えていますでしょうか。自民党支持者にお伝えしたいのですが、私は、幼少期にテレビで観ていた自民党内部における派閥間でバチバチに政治家が議論をしていた姿が好きでした。政権与党の地位が揺るがなかったことによる余裕からなのか、当時の政治家のプロ意識からなのかは分かりませんが、少なくとも今の自民党には私が子供の頃に感じたわくわく感はなく、極めて利己的・保身的に写ります。防衛費を拡張することに反対であることはもちろんですが、「非核三原則」を改めて核兵器を保有・共有するなどの話は言語道断であると考えます(憲法9条を盾に防衛費増額の外圧に毅然と対応してきたかつての自民党総裁のイズムはどこに行ってしまったのでしょうか)。
⑤首相には靖国神社に参拝してほしい
どちらとも言えない
【詳細な理由】
参拝によるプラスの評価・マイナスの評価は、時の首相がみずからの責任のもとに判断すれば良いため、私から参拝して欲しい・して欲しくないと評価する話ではないと考えます。
⑥社会福祉など政府のサービスが悪くなっても、お金のかからない小さな政府の方が良い
どちらとも言えない
【詳細な理由】
超少子高齢化に伴う労働者人口減少という政策課題との関係では、現役世代の負担軽減と持続可能な社会保障制度の維持が重要です。Q3の②でお伝えしたように、国民民主党の主張する給与所得者控除等の壁の引き上げとOTC類似薬の健康保険からの適用除外、無価値医療の健康保険からの適用除外などによる医療費の歳出削減などが有効と考えます。国家による社会福祉サービスの質を極端に低下させることなく、国民の自助を促す政策が今後の日本社会にとっては必要なのではないかと考えます。
⑦公共事業による雇用確保は必要だ
⑧当面は財政再建のために歳出を抑えるのではなく、景気対策のために財政出動を行うべきだ
どちらかと言えば反対
→どちらともいえないに訂正します。
【詳細な理由】
現在の物価高は円安が大きな要素であると考えます。エネルギー自給率や食料自給率の低い日本にとって、輸入品の値上げとなる円安は生活品に対する物価高を導きます。円安は、日本から海外に円が売られることによって、海外からみた円の価値が下がることで発生します。私は、アベノミクスによる金融緩和と財政出動(公共事業の増加も含む)により市場に多く出回った円が、貯蓄から投資への号令のもと、海外の金融商品(オルカンなど)に流れている点が、行き過ぎと感じられる円安の原因になっているのではないかと考えています。プライマリーバランスを無視した財政出動が物価高を凌駕(りょうが)するほどの好景気に繋がるものとは想定し難く、特に金融緩和による財政出動は更なる円安を誘発する原因にもなりかねないと考えます。なお、プライマリーバランスを維持した上での減税政策(財政出動)は大いに賛成です。
⑨時限的又は恒久的に消費税率を引き下げるべきだ
どちらかと言えば賛成
【詳細な理由】
全般的に物価高ですが、生活保障との関係からすると、食料品に対する消費税の減税は最優先事項といえます。そもそも食料品の消費税率が8%とされた趣旨は、生活必需品に対する負担軽減にあります(消費税の逆進性の緩和)。同趣旨からすれば、物価高による生活苦の状況で、食料品等の消費税率をゼロとすることは相当です。他方、10%の消費税率は、主に社会保障費の財源確保という観点から慎重な検討を要すると考えます。
政権与党は、現金給付を公約としていますが、千葉県知事の熊谷さんも懸念を示したように、現金給付は地域行政の事務的なコストを伴います(2025/6/14毎日新聞【現金給付事務「自治体を疲弊させる、うんざり」千葉知事が苦言】)。食料品の消費税率の減税がいま政府が最優先で取り組むべき合理的・効果的な政策であると考えます。なお、政権与党は税収の上振れを財源に現金給付を公約しましたが、食料品の減税も同等の財源で足ります。
⑩所得税の非課税枠をもっと引き上げるべきだ
どちらかと言えば賛成
【詳細な理由】
国民民主党の主張する基礎控除や給与所得控除の引き上げによる減税政策は、労働人口の手取りを増やすという点で物価高対策となります。さらに、国民民主党の主張する給与所得控除等の引き上げは、就労意欲・勤労意欲を高める機能もあるため、年齢を重ねても長く働く動機付けとなると私は考えています。労働の機会は認知機能の低下を遅滞させる結果にも繋がりますから、社会保障費の抑制という観点からも合理的です。
世代を問わず、長く働くことへのモチベーションを高める政策(自助を促す政策)は、超少子高齢化により年金も含めた社会保障制度の維持が難しい状況に鑑みると、必要な政策と思います。壁が160万円に引き上げられたとは言うものの、与党案と国民民主党案は、就労意欲・勤労意欲を高める意味合いでは雲泥の差があります(2025年2月27日【日テレNEWS】要参照)。
徹底した歳出改革により、労働者人口の就労意欲・勤労意欲を高める政策を実施することが、超少子高齢化に伴う労働者人口の減少という社会問題を解決するにあたっては、①早期に経済的基盤を確立することによる将来設計の実現(少子化対策)、②就労意欲・勤労意欲の向上(労働者人口の減少対策)、③就労機会の伸長による高齢者の認知機能の低下の遅滞(高齢化対策)ということとの関係で、極めて効果的・効率的であると考えます。
⑪日本銀行は政策金利を引き上げるべきだ
どちらとも言えない
【詳細な理由】
市中銀行との対話による日本銀行の独立性を尊重すべきと考えます。
⑫企業が納めている法人税率を引き上げるべきだ
どちらかと言えば賛成
→どちらとも言えないに訂正します。
【詳細な理由】
基本的に増税路線には反対ですが、法人税率の引き上げにより内部留保ではなく構成員への賃金として支出するという流れが期待できないではないようにも思います。ただ、ジョブ型雇用の推進や人手不足による人材の流動化・活性化で構造的にみると賃上げが期待できる外部環境にあります。そのため、法人税率の引き上げにより刺激する必要はないとも思います。他方、歳出改革を実行してもなお、社会保障費との関係で財源が必要な場合は、担税力のある法人に対する課税は検討対象の1つとすべきように思います。
⑬高齢者の医療費の窓口負担割合を3割に引き上げるべきだ
どちらかと言えば賛成
【詳細な理由】
現在の日本は、世界的に類を見ないほどの超少子高齢化です。過去の日本と比較して、支える人口に比して、支えられる人口の割合が多いことは明らかですから、社会保障制度の給付水準を引き下げて、現役世代の負担を抑制する必要があります。具体的には、70歳以上の窓口自己負担割合の一律3割負担の他、OTC類似薬の健康保険からの適用除外、無価値医療の健康保険からの適用除外などによる医療費の歳出削減(推計2~7兆円の医療費削減)が有効です(集英社オンライン2025.2.20【「健康保険料高すぎ!」「もう限界」国民の負担を増やす前に厚労省がやるべき、2~7兆円もの医療費を削減できる3つの医療改革とは】)。
⑭外国人労働者の受け入れを進めるべきだ
どちらとも言えない
→どちらかといえば反対に訂正します。
【詳細な理由】
外国人労働者の受け入れは、労働者人口の減少という観点から必要性は理解できるものの、治安維持等から弊害の声も強く感じます。業務効率化を推進して、日本人の労務価値を提供する機会(雇用の機会・雇用の価値)を最大化することは、少子高齢化に伴う労働者人口の減少という社会問題との関係でも重要です。また、適度に働く機会があることは、「老化防止」や「健康維持」という社会保障との関係でも有効です。安易な外国人労働者の受け入れに頼らず、日本国内における日本人の労務価値をより大切にする政策が重要と考えます。
⑮治安を守るためにプライバシーや個人の権利が制約されるのは当然だ
どちらとも言えない
【詳細な理由】
治安の維持という国家権力の発動に対しては、プライバシー権などの個人の基本的人権を制約する機能があるため、制約されて当然という意識を権力者側が持つことは極めて危険です。とはいえ、治安維持も極めて重要な政策課題となるため、双方のバランスが重要です。なお、治安維持の政策については、こちらの投稿もご覧ください(【減税政策】ふるさと納税の仕組みを応用して防犯・見守り社会のインフラを整備する方法とは?)。
⑯公務員の人数や給与を抑制すべきだ
どちらとも言えない
【詳細な理由】
公務員の人件費は増やさずとも、行財政改革により政界を含めた行政の業務効率化を実現することで、公的インフラともいえる民間需要(高齢者の足の問題や食の安全保障に関する米の問題)に、より多くの人や時間を割けるようになると、公務員個人にとっても、国家・地域社会全体にとってもメリットがあると考えます(公務員の兼業・副業推進)。この点については、こちらの投稿もご参照ください(【行財政改革】この先6年間の研究課題!予算を使い切らなければ、次年度の予算が減らされる仕組みは何とかならないのか?公務員へのインセンティブ制度の導入とともに考えて発信します!)。
⑰雇用の流動化を進めるべきだ
賛成
【詳細な理由】
少子高齢化に伴う労働者人口の減少により日本社会はどこも人手不足です。新卒採用や転職市場が活況であることからみても、兼業・副業を含めた雇用の流動化・活性化は、個人の価値を高める要素になるように思います。また、高齢者の足の問題や食の安全保障としての米農家の人材不足の問題など、公共性の高い民間需要に対して、公務員の雇用体系を流動化・活性化させることによって、供給を仕掛けていくという方法も有益と考えます。
⑱政策研鑽や人材育成のため、党内に派閥/政策集団は必要だ
どちらとも言えない
【詳細な理由】
政策研鑽や人材育成のために機能していれば問題ないですが、機能していない場合は単なる仲良し集団に過ぎないといえます。もう少し、組織ではなく個人として責任を追って活動する政治家が増えると、組織に対するプレッシャー(党内議論の活性化・透明化)に繋がるように思います(こちらの投稿もご参照ください【完全無所属で活動する理由とは?】)。
⑲男性同士、女性同士の結婚を法律で認めるべきだ
どちらかと言えば賛成
【詳細な理由】
先の衆議院選挙では、私は以下のような意見を持っていました。
~~~~~
基本的には、先に述べた選択的夫婦別姓と同じ理由で賛成となります。ただ、微妙に賛成の程度が異なるという理由は、同性婚に対する国民感覚です。選択的夫婦別姓における苗字が個人のアイデンティティー(自分らしさ)に紐づくという感覚ほどに同性婚により自らのアイデンティティー(自分らしさ)が満たされるという感覚は国民に浸透していないようにも思います。何でもかんでも権利であると主張すれば、憲法上の権利となる訳ではありません。同性婚の話が何でもかんでも主張している権利とは私個人としては一切思いませんが、国民感覚が追いついているかというと選択的夫婦別姓と比較して、少し劣るように思います。そのため、個人的には賛成ですが、もう少し議論が必要のように考えます。
~~~~~
この間、札幌、東京、福岡、名古屋、大阪の全国5か所で6件、起こされていた戸籍上の同性のカップルに結婚が認められないのは憲法に違反するした集団訴訟で、5件の事件につき、高等裁判所が憲法違反と判断しました(残る1件は東京高裁で審理中:2025年3月25日NHK(【同性婚認めないのは憲法違反 大阪高裁 2審の違憲判決は5件目】))。最高裁判所がどのような判断をするかは分かりませんが、少なくとも、結論を示しているすべての高等裁判所が違憲と判断するほどに議論が深まっている状況からすると、現時点に至っては、先に述べた選択的夫婦別姓と同様かつ同程度の理由による賛成の意見です。
⑳国会議員の議席や候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制を導入すべきだ
どちらとも言えない
【詳細な理由】
国会議員に女性が少ない点を問題と感じつつも、国会議員に男性が多くとも女性の意見を適切に拾って議論できていれば問題ないという思いもあります。また、クオータ制の導入により、女性に席を割り当てることありきとなってしまう懸念もあります(イヤイヤやらせるということは本末転倒です)。男性であっても女性であっても被選挙権は平等ですから、女性が被選挙権を行使することが難しい環境があるのであれば、そのような環境を改善することが本質的な問題に対する解決策なのではないかと考えます。
Q5 次に挙げる争点について、あなたのお考えはA・Bのどちらに近いでしょうか。
Aに近い
どちらかと言えばAに近い
どちらとも言えない
どちらかと言えばBに近い
Bに近い
①
A:日本にとって中国は脅威である
B:日本にとって中国はパートナーである
どちらとも言えない
【詳細な理由】
米国とともに日本の輸出・輸入の最大の貿易相手国である中国との関係を強化することは、日本にとって重要ですが、社会主義を採用する国家体制に対しては、民主主義を採用する我が国とは異なる価値観を根底に有することも多いため、適度な距離感は必要と考えます。
②
A:日米関税交渉では、速やかな合意を目指すため、米国の要求を多少受け入れるのはやむをえない
B:日米関税交渉では、合意まで多少時間がかかっても、米国の要求受け入れには慎重であるべきだ
どちらかと言えばBに近い
【詳細な理由】
トランプ政権の対応をみると良く言えば流動的、悪く言えば場当たり的な印象もあるため、どちらかといえば、慎重に交渉する必要があると思います。4年後にアメリカ国民がどのような選択をするかも分からない訳ですから、拙速な対応は厳禁のように思います。
③
A:社会的格差が多少あっても、いまは経済競争力の向上を優先すべきだ
B:経済競争力を多少犠牲にしても、いまは社会的格差の是正を優先すべきだ
どちらとも言えない
【詳細な理由】
経済競争力の向上なくして、社会的格差を是正する税収の発生はあり得ません。どちらを優先するかという優劣の話ではないように思います。
④
A:国内産業を保護すべきだ
B:貿易や投資の自由化を進めるべきだ
どちらかと言えばBに近い
【詳細な理由】
保護主義よりも自由主義の方が結果的に国内産業の国際的な競争力を促して、経済的発展を遂げて成長してきた歴史があるように思います。自由主義を基軸として、ある程度の保護主義で調整するというこれまでの在り方が理想的のように思います。
⑤
A:いますぐ原子力発電を廃止すべきだ
B:将来も原子力発電は電力源のひとつとして保つべきだ
どちらとも言えない
【詳細な理由】
現時点では少なくとも今の程度は必要ですが、長い目で見たときには依存度を下げるべきと考えています。東日本大震災による福島原子力発電所の問題は今なお解決できていないままですが、経済的・財政的観点から原子力発電所の依存は続いています。エネルギーの国内自給率を高めることは、経済的観点からみると国家の独立性を保持するために必要不可欠な要素です。資源の乏しい日本ですが、段階的な廃炉を見据えて、原子力に代わるエネルギー資源の研究・開発や近い将来の消費電力増加が見込まれるデータセンターなど産業用消費の省エネ研究・開発に人的・物的資本を継続的に投入する必要があると考えます。
⑥
A:国債は安定的に消化されており、財政赤字を心配する必要はない
B:財政赤字は危機的水準であるので、国債発行を抑制すべきだ
どちらとも言えない
【詳細な理由】
積極的な財政出動により景気・経済を刺激するという方向性も理解できますが、それに伴って、国家としての正確なキャッシュフローが見えにくくなるという弊害もあります。また、いたずらな金融緩和は、貯蓄から投資への号令のもと、海外の金融資産に個人投資家の目が向けられる傾向にある現状に鑑みると、円安を助長するおそれもあると危惧しています。食料品の消費減税や給与所得控除等の引き上げにより失われる財源を社会保障制度改革や防衛費の見直しなどにより健全に積み上げていく姿勢が、世界的に類をみないほどの超少子高齢化社会における持続可能な国家経営には重要と考えます。
⑦
A:気候変動問題に対応するため、生活水準を犠牲にすることも必要だ
B:生活水準を犠牲にするほど、気候変動問題への対応は重要問題ではない
どちらとも言えない
【詳細な理由】
いずれも重要と考えます。
⑧
A:マイナンバーの活用・普及を推進すべきだ
B:マイナンバーの活用・普及を規制すべきだ
どちらかと言えばAに近い
【詳細な理由】
業務効率化との関係で、マイナンバーの活用・普及は重要です。現場の混乱やデジタル化への対応が難しい方々への配慮は必要ですが、基本的には活用・普及が相当と考えます。
⑨
A:企業・団体にも政治活動の自由がある
B:企業・団体献金は全面禁止すべきだ
Bに近い
【詳細な理由】
寄付・献金を受ければ、寄付者・献金者の顔色を伺って活動することは、義理・人情のある人間であれば当然と思います。憲法43条1項は、国会議員は「全国民を代表する」と規定しています。全国民の代表という憲法上の要請からすると、寄付者・献金者の顔色を伺った活動を強く誘発する企業団体献金は全面禁止とすべきです。
また、国政政党には政党助成金が交付されています。政党助成金はリクルート事件など、企業と政治家を巡る政治とカネの問題に対する解決策として導入された制度です。それにもかかわらず、企業団体献金が廃止されていない現状には強い違和感を覚えます(全体としてみたときに、法制度としての整合性に疑問があります)。仮に、現行の政党助成金で国政政党が運営できないというのであれば、国家経営者としての資質に、強く疑問を感じます。
なお、国民民主党は、企業・団体献金禁止の対象から政治団体を除外している点につき「抜け道になる可能性がある」として、結果的に、立憲民主党などの提出する企業・団体献金禁止の法案に賛成しませんでしたが、現行法よりマシになるのであれば、指摘する抜け道があったとしても、自民党・公明党の主張する規制強化よりは実行性あるものと感じるため、この点は本当に対決より解決を志向しているのか強く疑問に思いました(2024/12/1産経新聞)。
⑩
A:一票の格差是正のためにも、参議院選挙区の「合区」は許容されるべきだ
B:参議院選挙区の「合区」を解消するためにも、一定範囲内の一票の格差は許容されるべきだ
Aに近い
【詳細な理由】
民主主義の原則は1人1票です。1票の格差の問題は、民主主義の根幹にかかわります。日本社会は交通網もインターネットのインフラも十分に整備されています。交通網が発達せず、インターネットもなかった時代と比較すると、地理的環境にかかわらず、各地域の問題を汲みとりやすい環境にあります。また、「合区」を解消して地域代表としての性質を強化することは、地域との癒着の懸念もあります(他の選挙区の有権者からみると「なぜあの人が当選するんだ??」と思うことも少なくないです)。「合区」の解消による目的・効果は、憲法上の価値である1票の価値の平等という要請に優越するものではないと考えます。
⑪
A:日本は二大政党制を目指すべきだ
B:日本は多党制を目指すべきだ
どちらかと言えばBに近い
→Bに近いへ訂正します。
【詳細な理由】
多党化の傾向にある近年の選挙結果が物語っていると思います。2大政党制の方が多数派となった政党による迅速な意思決定が実現できますが、これまで圧倒的多数派として政権を担ってきた自民党・公明党の政権に対する疑問・不信が現在の多党化に表れています。大統領制を採用する米国と異なり、議院内閣制を採用する日本では、多少の迅速性を阻害しても、議論が中心となる多党制が適しているように思います(2大政党制でも党内議論が活発化しているのであれば問題ないですが、現在の大多数の国政政党からは、党内における自由闊達な議論が一切感じられません)。インターネットの発達により情報の透明化が進んでいます。単に反対しているだけの組織(人)なのか、対案を出して議論をしている組織(人)なのか、有権者が容易に判断できる時代ですから、多党制が適していると考えます。
⑫
A:わたしは、自分を支持した地域や団体の代表というよりも、すべての国民の代表である
B:わたしは、すべての国民の代表というよりも、自分を支持した地域や団体の代表である
Aに近い
【詳細な理由】
良い質問です。憲法43条1項は、国会議員は「全国民を代表する」と規定しています。すべての国民の代表であることは、憲法が国家権力の構成員である国会議員に求めるものです。政党は、あくまでも、憲法21条1項の表現の自由に由来する結社の自由という解釈により認められている存在に過ぎません。政党所属の国会議員における全国民の代表であるという意識の欠如こそが、国政における現在の政治不信に大きく繋がっているものと考えます。この質問に対する政党所属の候補者の回答で、国民の利益を見ずに政党の利益をみて活動する候補者なのか、政党を通じて国民の利益をみている候補者なのかが顕在化すると思います。
⑬
A:選挙戦では、所属政党の政策や実績よりも、自分自身の人となりや政見を重点的に訴えたい
B:選挙戦では、自分自身の人となりや政見よりも、所属政党の政策や実績を重点的に訴えたい
Aに近い
【詳細な理由】
完全無所属となるため、候補者個人をみて判断いただくより他ありません。
夫婦の名字についておうかがいします。
Q6 「夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の名字を称することを、法律で認めるべきだ」という意見について、あなたは賛成ですか、それとも反対ですか。
1.賛成
2.どちらかと言えば賛成
3.どちらとも言えない
4.どちらかと言えば反対
5.反対
【回答】
1.賛成
【詳細な理由】
憲法13条は個人の尊厳を規定します。個人の尊厳に対する制約を正当化できる理由は、「公共の福祉」という他者との人権衝突を調整するためというやむを得ないものに限られます。苗字が個人のアイデンティティー(自分らしさ)に紐づくという国民感覚は共通と思います。選択的夫婦別姓ですから、夫婦同姓の選択肢が廃止される訳ではないです。選択肢を広げるだけの話ですから、選択的夫婦別姓の導入を否定する理由はないと考えます。
手続的な煩雑性という懸念は、個人の尊厳を制約する根拠にはなりません。国家としては、個人の尊厳という憲法の要請を尊重していく必要があります。この点、子どもがいる場合は、子どもの視点からも考える必要があるとの意見もありますが、親が子どもの名前を付けるように、子どもに対しては親のいずれかの苗字を名乗らせるかを決めなければならないという法制度とすれば、子どもの視点からも混乱が生じることはないと考えます。
余談ですが、いつまで選択的夫婦別姓の議論を続けるのでしょうか。政権与党の自民党が党議拘束を外して決議すれば、どのような結論となるかは目に見えているように思います。それにもかかわらず、党議拘束を外すことのできない自民党の姿には、私が幼少期の頃、党内でバチバチに議論していた姿勢を一切感じることができず、保身的・閉鎖的な組織になってしまったと感じざるを得ません。国政に対しての個人的な感想としては、自民党が党内でもう少し政策次第で袂(たもと)を分かつようになると、政策議論が活性化されて、国政全体として良い方向に進んでいくのではないかと考えています。なお、現在の自民党議員は、組織の決定に縛られ過ぎていて、個々の政治家に個性を感じることができません。誰がやっても変わらないという一有権者としての感覚は、党議拘束が強すぎる組織の在り方に対する疑問と思います。
Q7 「夫婦が同じ名字を称する制度は変えず、結婚前の名字を通称として使える機会を拡大すべきだ」という意見について、あなたは賛成ですか、それとも反対ですか。
1.賛成
2.どちらかと言えば賛成 (SQ7を飛ばして、Q8にお進みください)
3.どちらとも言えない
4.どちらかと言えば反対
5.反対
【回答】
4.どちらかと言えば反対
SQ7【Q7で「反対」「どちらかといえば反対」と答えられた方におたずねします】 直前のご回答の理由は、次のどちらに近いでしょうか。
1.あくまで選択的夫婦別姓制度を実現すべきだと思うから
2.あくまで夫婦は同じ名字を名乗るべきだと思うから
【回答】
- あくまで選択的夫婦別姓制度を実現すべきだと思うから
【詳細な理由】
Q7のとおりです。
ふたたび、全員におうかがいします。
Q8 首相は、会食の土産代わりとして一人あたり10 万円の商品券を国会議員に配りました。社会通念上の儀礼の範囲を超えているという批判がある一方、政界と一般社会は同列に論じられないという意見もあります。あなたは、政治活動以外の政治家同士の寄付(結婚祝いや香典は除きます)について、どこまでが許容範囲と思いますか。
1.政治家同士の寄付は一切行うべきではない
2.一人あたり1万円相当までならありえる
3.一人あたり5万円相当までならありえる
4.一人あたり10 万円相当までならありえる
5.時と場合によっては一人あたり10 万円相当を超える寄付もありえる
【回答】
1.政治家同士の寄付は一切行うべきではない
【詳細な理由】
【政治資金収支報告書データベース】を閲覧して感じるのですが、政治家同士の寄付・献金があまりにも多すぎるように思います(特に自民党の国会議員)。寄付献金を受けたものは、受けた寄付献金を自由に使って良いという考えもあるかもしれませんが、他方で、寄付献金者は、その政治家に対して寄付献金をしたのですから、その寄付献金は他の政治家の寄付献金の原資とすべきでないとの考えもあって良いように思います。お金に色はないといいますが、色を付けることが禁じられている訳ではありません。政治家同士の寄付は一切禁止として、政治とカネの流れを明確化することが必要と考えます。また、このような考え方を貫徹すると、政治家の資金管理団体の資金は、一身専属性を有するとして、当該政治家が引退・死亡した場合には、解散・国庫帰属とすべきと考えます(2024年12月4日しんぶん赤旗【安倍元首相の政治資金、昭恵氏が無税で引き継ぎ】)。
憲法についておうかがいします。
Q9 あなたはいまの憲法を変える必要があると思いますか、それとも変える必要はないと思いますか。
1.変える必要がある
2.どちらかと言えば変える必要がある
3.どちらとも言えない
4.どちらかと言えば変える必要はない (SQ9を飛ばして、Q10にお進みください)
5.変える必要はない
【回答】
5.変える必要はない
【詳細な理由】
こちらの投稿をご参照ください(【国家観と財源】司法試験の公法系全受験者2位のイズムを受けた弁護士兼政治家が発信する憲法9条の改憲問題の考え方とは?(アップデートver))。憲法とは国家権力を規制して、国民・市民を守るルールです。1有権者として、現在の大多数の政治家に、国家権力の規制という自らを律するルールの変更につき、利己的な判断なく議論できる人々であるという信頼が私にはありません。
ふたたび、全員におうかがいします。
Q10 あなたが所属されている政党は (無所属の場合、あなたご自身は) 、選挙後、以下の政党との連立政権に参加しても良いと考えますか。
選挙結果にかかわらず連立を組むべきだ
選挙結果次第では連立もありうる
選挙結果にかかわらず連立はありえない
自分が所属する政党
① 自民党 選挙結果にかかわらず連立はありえない
② 立憲民主党 選挙結果次第では連立もありうる
③ 公明党 選挙結果にかかわらず連立はありえない
④ 日本維新の会 選挙結果にかかわらず連立はありえない
→選挙結果次第では連立もありうるに訂正します。
⑤ 共産党 選挙結果次第では連立もありうる
⑥ 国民民主党 選挙結果次第では連立もありうる
⑦ れいわ新選組 選挙結果にかかわらず連立はありえない
⑧ 社民党 選挙結果にかかわらず連立はありえない
⑨ 参政党 選挙結果にかかわらず連立はありえない
⑩ 日本保守党 選挙結果にかかわらず連立はありえない
【詳細な理由】
完全無所属ですが、一応回答しました。①自民党・③公明党は政治とカネの問題につき、国家経営を担う組織としてのコーポレートガバナンスの機能不全を感じます。②立憲民主党は、財源を比較的丁寧に検討して現実的な政策を提案していると感じます(食料品消費税の減税、選択的夫婦別姓、企業団体献金の禁止など)。ただし、厚生年金の流用に対する賛成は、強く疑問でした。④日本維新の会は、医療費などの社会保障制度への改革姿勢は合理的と感じます。ただ、身を切る改革が下火になっているのが残念です。⑤共産党は、防衛費に対する疑問を呈している点や政治とカネの問題について強く切り込む姿勢は評価できると考えます(しんぶん赤旗は政界の週刊文春と思います)。他方で、消費税の減税と社会保障費の削減反対など財源の説明が難しいようにも感じます。⑦れいわ新選組、⑧社民党、⑨参政党、⑩日本保守党は、理念の部分で共感できる点もあったり、なかったりです。ただ、歳出を伴う政策の財源につき具体性に乏しいと感じる点も多々あります。⑥国民民主党の壁の引き上げは、非常に良策と思います。ただ、プライマリーバランスを維持した財源の説明ではない点に、個人的にはやや物足りなさを感じます。
総ずるに、⑥国民民主党の主張する壁の引き上げにより現役世代の負担軽減や就労意欲等の向上を図って、社会保障制度に依存し過ぎない自助を促し、④維新の会のような社会保障費や⑤共産党のような防衛費の歳出改革により、②立憲民主党のようなプライマリーバランスを維持する意識を持った形での制度設計が、今後の日本社会にとっては良策と考えています。
Q11 国会審議のあり方についておうかがいします。
現在、国会の審議時間の多くは大臣など政府関係者への質疑に当てられています。これに対し、「質疑を減らして議員同士の討議を増やすべきだ」という意見があります。あなたはこの意見に賛成ですか、それとも反対ですか。
1.賛成
2.どちらかと言えば賛成
3.どちらとも言えない
4.どちらかと言えば反対
5.反対
【回答】
- どちらとも言えない
→4.どちらかと言えば反対に訂正します。
【詳細な理由】
それぞれ重要ですが、性質が異なると考えます。国会議員と大臣などの政府関係者への質疑は国会(立法府)対内閣(行政府)の構図です。他方、議員同士の討議は、基本的には国会(立法府)対国会(立法府)の構図になります。議員同士の討議は、党内議論を透明化することにより手当可能と思います。どちらかといえば、国会審議としては、立法府対行政府の質疑時間を多く採用している現在の在り方で良いのではないかと考えます。
Q12 政治とマスメディア、インターネットの関係について、さまざまな意見があります。
そう思う
どちらかと言えばそう思う
どちらとも言えない
どちらかと言えばそう思わない
そう思わない
①インターネットによって、マスメディアの影響力は低下した
どちらかと言えばそう思う
→そう思うに訂正します。
【詳細な理由】
マスメディア以外に情報を取得する機会がなかった時代と比較すると、インターネットの登場により情報を獲得する手段が多様化しました。インターネットがなかった時代と比較すると、情報格差は是正されて、マスメディアの影響力が低下したことは明らかと思います。
②新聞やテレビは、正確な事実に基づいて報道している
どちらかと言えばそう思う
【詳細な理由】
良い質問です。報道している事実は正確と思います。ただ、報道されない事実や報道のされ方についても目を向ける必要があります。例えば、世論調査における政党支持率です。NHKなどの各種旧来型のメディアは、電話調査を採用しています。しかも「固定:携帯=4:6」など固定電話の利用率に比して採用率が高いです。そのため、東京都議選をみても分かるように、事前の世論調査の結果と選挙結果が一致しない傾向にあります。報道している内容が事実ではあるものの、実態を正確に反映した事実であるか疑問に思うことも多々あります。
③SNS 上には、新聞やテレビが伝えない「真実」の情報がある
どちらとも言えない
【詳細な理由】
「真実」は神のみぞ知る話となるため、何とも言えませんが、新聞やテレビでは伝えられない話もSNSを通じて、生の情報として発信されることもあります。そのような生の情報も総合して検討すると、より「真実」に近づくこともあるかと思います。他方、SNSの情報が生の情報でなければ、SNSの情報により「真実」から遠ざかることもあると思います。例えば、災害時にSNSで発信される情報が事実に基づくのであれば「真実」の情報といえますし、事実に基づかないのであれば真実の情報とはいえません。ケースバイケースと考えます。
④SNS での発信は、自分の名前や人となりを人々に知ってもらう効果がある
⑤SNS での発信は、自分の意見や政策を人々に知ってもらう効果がある
⑥SNS での発信は、政策について人々と議論する手段として有効だ
⑦SNS での発信は、自分の得票を増やす効果がある
⑧SNS での発信は、相手勢力の支持を下げる効果がある
どちらかと言えばそう思う
【詳細な理由】
SNSは、一次的な情報を本人が容易に発信できる伝播性を有するツールです。利用方法によっては、④から⑧の効果はあります。ただし、利用方法を間違うと逆効果もあります。
⑨プラットフォーム事業者には、誤情報や偽情報をチェックする法的義務を負わせるべきだ
どちらかと言えばそう思う
【詳細な理由】
誤情報や偽情報により個人や企業が損害を被るケースも多々発生しています。プラットフォーマーでなければ、迅速な被害回復のための措置を講ずることができないことも多々あります。場を提供する者の役割として、ある程度の管理責任は必要のように考えます。
⑩未成年のSNS 利用を禁止すべきだ
どちらかと言えばそう思わない
【詳細な理由】
一口に未成年といっても幅が広いため、成熟性の度合は様々です。情報リテラシーを学ぶ能力が低い時点までは禁止という方法もあるかもしれませんが、禁止よりも適切な利用方法を教育する機会(情報リテラシー)を与えることが、根本的な問題解決に繋がると思います。
~~~~~
以上
朝日新聞アンケートに対する詳細な回答を考えて発信しました!
~~~~~~~~~~~
個別連絡のできるLINE公式アカウントです!
ご意見・ご感想お待ちしています!
応援メッセージやラジオのトークテーマも大歓迎です!
「期日前投票行って来た!」のご報告も感涙です!!
「10人連れて行って来た!」は大感涙です!!笑
毎日23時からYouTubeを利用した生配信(ライブ)を実施します!
(15分から30分ぐらいを予定しています)
なお、翌日12時頃にホームページの音声配信にもアップ予定です。
ぜひともお楽しみいただけますと幸いです!
お知らせ配信専用のXアカウントです。
みなさまフォローしてご活用お願いします!
<選挙ドットコムからご覧の方へ>
すべての情報は公式ホームページにあり!!
是非ともご来訪ください!!
~~~~~~~~~~~