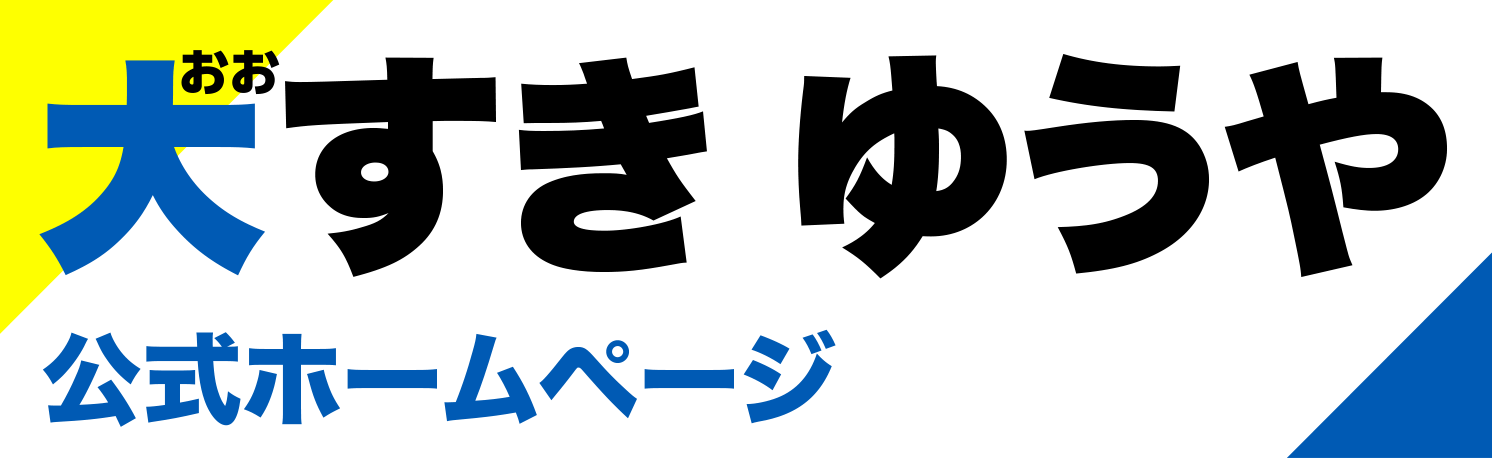ライブ配信業者に対価を支払ってライブ配信を実施する行為は、公職選挙法の運動買収となるのか?何が問題でどのように考えるべきなのか?という点を弁護士兼政治家として徹底的に考えて発信します!!
千葉・市原出身|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです。
千葉県知事選挙と千葉市長選挙が近づいています。
ポスター掲示場もあちこちに設置されています。
これをみた妻が言っていました。
「初めからポスター貼って設置すれば良いのにね~」
本当にそう思います(笑)
百歩譲ってデジタルサイネージが難しくとも、ルールの変更で効率化できるはずです。
現行法は選挙が始まってからでないと選挙運動ができないというルールとなるため、各所に掲示場だけ設置されて、選挙が始まってから選挙ポスターを貼る流れになっています。
~~~~~~~~~
選挙が始まらなければ選挙運動はできない。
ただし、ポスターの貼付はこの限りでない。
~~~~~~~~~
これだけで相当に業務効率化できると思うのですが、いかがでしょうか。
さて、本日の本題です!!
率直に思うところがあったため、予定を変更してお送りします。
今回のテーマは、
ライブ配信業者に対価を支払ってライブ配信を実施することの適法性
です!
コメンテーターを生業としている訳ではないため、政治活動での定期的な配信内容に時事ネタを投稿することは控えていますが、今回のテーマは、公職選挙法に関する理解を整理しておくために私自身にとっても有益と思い、考えて発信することしました!
それでは、中身に入ります!
初めに、私の結論をお伝えしておきます。
私は業者に対価を支払ってライブ配信する行為を
適法
と考えています。
以下、理由をお伝えします。
まずもって、今回のテーマを考えるにあたっては、以下の投稿の検討が非常に有益です。
【ポスター貼りなどを外部業者に委託するための費用の支出は適法か?公職選挙法が規制する「選挙運動者に対する買収禁止」との関係について考えて発信します!(公職選挙法221条1項1号)】
私自身の過去の投稿です!
将来のために役に立つはずと思って投稿しましたが、こんなに早く役立つときが来るとは思いませんでした笑
川越市長選挙の応援演説の投稿を除けば、最近のアクセス数が一番多い投稿です。
今回の問題を考えるにあたって重要な基礎知識となるため、是非ともご一読ください。
要するに上記投稿は何を整理しているかというと、
~~~~~~~~~~~~~~~
①公職選挙法の買収罪には、投票買収と運動買収がある。
②運動買収にあたるか否かは、依頼する行為が選挙運動にあたる行為か否かによる。
③選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者のため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘、その他諸般の行為をすることをいい、選挙に関し候補者のために行われる行為は、たとえ機械的な労働であっても、一般には、当該候補者のため投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為であることを否定しがたく、その行為の目的いかんによっては選挙運動にあたるものの、選挙演説のような、選挙民に対する投票の直接の勧誘行為は、その行為に出ること自体をもって特定の立候補者又は立候補予定者のため投票を得又は得させる目的があるものと認定することができるが、ポスター貼りや葉書の宛名書のような、選挙民に対する投票の直接の勧誘を内容としない行為は、これらの行為を自らの判断に基づいて積極的に行うなどの特別の事情があるときに限り、特定の立候補者又は立候補予定者のため投票を得又は得させる目的があるものと認定することができる(最高裁判所昭和53年1月26日)。
~~~~~~~~~~~~~~~
ということをお伝えしています。
③について簡略化すると、
選挙民に対する投票の直接の勧誘を内容としない行為は、これらの行為を自らの判断に基づいて積極的に行うなどの特別の事情がある場合に限って、特定の立候補者又は立候補予定者のため投票を得又は得させる目的がある(選挙運動にあたる)としています。
この点、ウグイス嬢が有権者に対する投票の直接の勧誘を内容とする行為であるのに対し、ライブ配信行為は、候補者が有権者に投票の直接の勧誘を呼びかける行為を手助けするものに過ぎず、ライブ配信行為自体は、投票の直接の勧誘を内容としない行為といえます。
そこで、公職選挙法の運動買収にあたるか否かを判断するにあたっては、ライブ配信行為が「自らの判断に基づいて積極的に行うなどの特別の事情があるとき」といえるのかという点を検討することなるのですが、これが極めて難問となります。
もちろん、「ライブ配信業者に対価を支払ってライブ配信を実施する行為が公職選挙法の禁止する運動買収にあたるか」という点が問題となった裁判例はありません。
が、
参考になりそうな裁判例としては、事件当時は許されていた選挙運動用葉書のポスティング(現行法は郵送のみ可です)の依頼を受けた者について、選挙運動用葉書をどのような方法で、選挙人の下へ届けるか(郵送するかポスティングするか)、あるいは具体的にどの選挙人に届けるかという選挙運動の内容・方法に属する事項につき、その決定に関与したり、裁量判断を委ねられている者を単なる労務者ということはできず、選挙運動者と認めるのが相当であるとしたものがありました(東京高等裁判所平成13年3月15日)。
ただ、正直、この裁判例だけではなかなか判断がつきません。
すると、未知の問題について、どのような結論となるかを考えることとなります。
その上で、私は、冒頭に述べたように、現行の公職選挙法は「ライブ配信業者に対価を支払ってライブ配信する行為」を許容していると考えています。
以下、理由を詳述します。
みなさん、政見放送の「持込ビデオ方式」をご存じでしょうか。
平たくお伝えすると、国政選挙で政党や政党所属の候補者は、事前にみずから録音・録画した政見を放送で使用できるとされています(公職選挙法150条1項1号、2号)。
特に、参議院選挙区選出議員の選挙の政見放送については、従前、スタジオ録画方式に限られていましたが、比較的最近といえる平成30年の法改正により、「できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにする観点」から、持込ビデオ方式が認められるようになりました(逐条解説公職選挙法改訂版1363-1364頁)。
その上で、公職選挙法は、持込ビデオの制作費用に公費負担を認めています(公職選挙法150条2項・公職選挙法施行令111条の5の1号、2号、公職選挙法規則17条の4、17条の7、17条の8:逐条解説公職選挙法改訂版1364-1365頁)。
~~~~~~~~~~~~~~
ちなみに、3年前の参議院選挙(千葉選挙区)の各候補者の収支報告書を確認したところ、概ね各人300万円ほどが公費負担として認められていました(ビックリしました!)。
さらに、ビラやポスターなどの公費負担制度と異なり、供託金没収ラインに届かない候補者でも持込ビデオの制作費は公費負担となっていました(重ねてビックリしました!!)。
(公職選挙法150条2項は、供託金没収ラインに届かない候補者への公費負担を認めないとする同法141条7項ただし書を準用していません)
「政党所属の候補者が優遇され過ぎでは??」
と強く思うところがあるのですが、別の機会に発信したいと思っています。
~~~~~~~~~~~~~~
話を戻します。
持込ビデオを制作するにあたっても動画を撮影する人、編集する人がいます。
持込ビデオとライブ配信には、編集的業務を事後的に実施するか、現場で実施するかの違いはあるにせよ、両者に大きな差はないと私は考えています。
仮にライブ配信ではなく録画配信であれば、持込ビデオと何ら変わりはありません。
先のとおり、持込ビデオの制作費は公費請求が可能です(公職選挙法150条2項)。
ライブ配信行為に必然的・付随的に伴う主体的・裁量的行為をもって、公職選挙法の運動買収として禁じられる選挙運動と評価することは、公職選挙法が持込ビデオの制作費の支出を許容している点と整合しないことからすると、ライブ配信行為は、最高裁判所が言及する「特別の事情があるとき」にはあたらないと評価することが適切ではないでしょうか。
端的に言えば、持込ビデオがOKでライブ配信がNGな理由が分からないということです。
以上の理由から、私は「ライブ配信業者に対価を支払ってライブ配信を実施する行為」は、「選挙運動者」に対する金銭の支払いにはあたらず、「選挙運動のために使用する労務者」への支払いとして、買収罪は成立しないと考えます。
進んで、公職選挙法は「選挙運動のために使用する労務者」への報酬支払いであっても、報酬の上限を規定していることとの関係を検討する必要がありますが、これについては、問題意識も含めて、以下の投稿と同じ思考回路となりますので、割愛します。
【ポスター貼りなどを外部業者に委託するための費用の支出は適法か?公職選挙法が規制する「選挙運動のために使用する労務者」に対する報酬制限との関係について考えて発信します!(公職選挙法197条の2)】
~~~~~~~~~~~~~~~~
今回改めて公職選挙法を調べた結果、上記投稿を少しだけ補足します。
公職選挙法は、ビラ・ポスターや持込ビデオの公費請求にあたって、公費請求できる契約の相手方は、ビラ・ポスターや持込ビデオの作成を「業」とする者に限定しています(例えば、ビラについては、公職選挙法142条10項、公職選挙法施行令109条の8、公職選挙法施行規則17条の4:逐条解説公職選挙法改訂版1196頁)。
要するに、「業者」に限定している訳ですが、利益なくして生業は成立しないですから、公職選挙法自体、費用支出の相手方が「選挙運動のために使用する労務者」といえる業者であれば、当該業者への支払を通じた人件費等の報酬支払につき、選挙費用の法定限度額(公職選挙法247条)を超えない限りにおいて、許容しているものと考えます。
~~~~~~~~~~~~~~~~
以上
ライブ配信業者への費用支出の適法性を弁護士兼政治家として徹底的に考えて発信しました!
~~~~~~~~~~~~~~~
個別連絡のできるLINE公式アカウントです!
ご意見・ご感想お待ちしています!
ボランティア希望のご連絡も大歓迎です!!
弁護士兼政治家大すきゆうやの執務報告書を月末にまとめてお届けする配信専用のLINE公式アカウントです!
政治は日頃から考えることが大事です!
是非とも友達登録お願いします!
ブログの投稿をお知らせする配信専用のXアカウントです。
みなさまフォローしてご活用お願いします!
<選挙ドットコムからご覧の方へ>
すべての情報は公式ホームページから発信します!!
是非ともご来訪ください!!
~~~~~~~~~~~~~~~