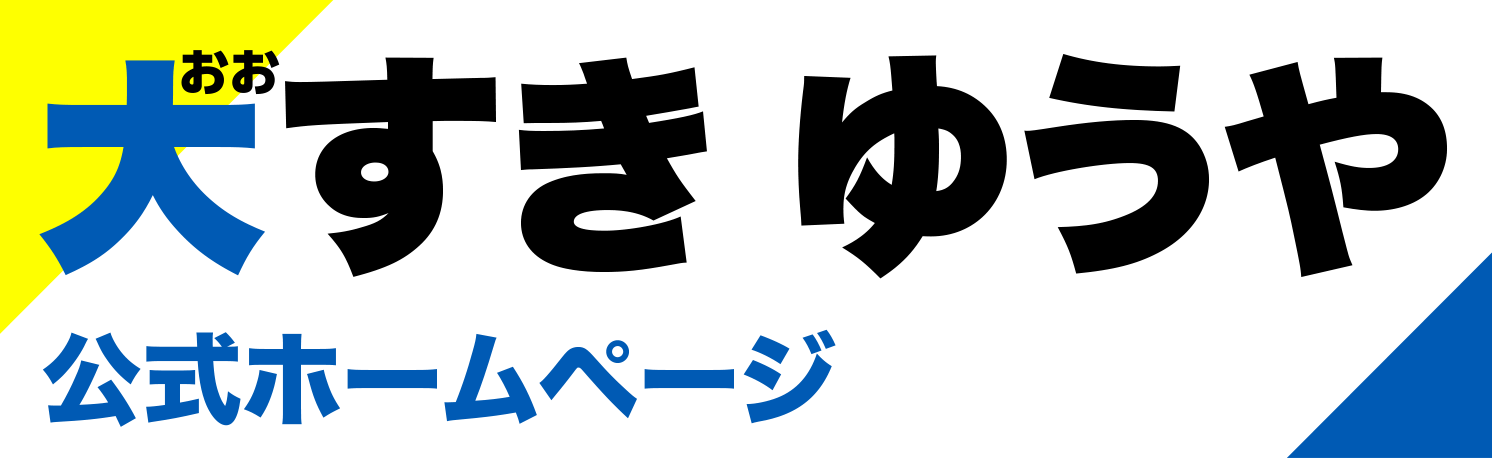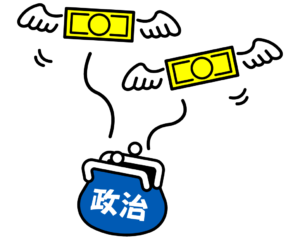日本の国政選挙である衆議院議員選挙(小選挙区)の供託金及び供託金没収ラインの妥当性とは? その1
千葉・市原出身|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです。
年末に向けてふるさと納税が活況です。
先日、千葉県選挙管理委員会へ収支報告書を閲覧しに行ったときに、「政治家の寄附禁止ルールブック」というリーフレットが置いてあったため、持ち帰りました。
政治家から有権者に対して寄附をすることは、票をお金で買う行為となるため、お金のかからない選挙の実現という観点から、強く禁止されているものとなります。
リーフレットの中で気を付けなければならないと思った点の1つに、選挙区へのふるさと納税の禁止という注意がありました。
私の活動拠点は、千葉・市原となるところ、住まいは千葉市となるため、ふるさと納税の余地があるとすれば、市原市となります。
私は寄附することができませんが、市原市にはLIONの生活用品やゴルフ関連の商品が充実していると思いますので、特に財源が豊富な都内在住の方々に向けて、強くオススメいたします!!
さて、本日の本題です!
本日は
選挙の供託金
について考えて発信します!
前回投稿したブログにて、共産党は政治とカネに対する強い問題意識を有する政党であると感じたことをお伝えしました。
私が立候補した千葉3区でも共産党に所属する加藤さんが立候補されていました。
結果的には、加藤さんの得票数は9297(得票率5.6%)となったため、衆議院議員選挙(小選挙区)における供託金没収ライン(有効投票数×10分の1未満=得票率10%未満)に届きませんでした。
その結果、供託金300万円及び選挙運動における公費負担の余地のあった費用(選挙ポスター約100万円、選挙ビラ約50万円、選挙葉書約28万円、選挙カー看板約20万円、事務所立札・看板約17万円など)が認められない結果となりました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
*なお、いずれの金額も収支報告書を閲覧した結果の千葉3区における各候補者が支出した費用の相場・平均を記載しています。
ちなみに、収支報告書には、選挙カーの看板費用は記載する必要がありますが、選挙カーの利用料(自動車の借り入れ、燃料費、運転手代)は公費負担があるにもかかわらず、選挙運動に関する支出とみなされないものとして、収支報告書に記載する必要はないとされています(公職選挙法197条2項・141条7項本文)。
公職選挙法を解説した逐条解説という文献には「候補者間でおおむね共通した経費であり、特に規制を要しないと考えられることから、選挙運動に関する支出でないものとみなされる」(1549頁)と述べられていますが、そんなことを言い出したら、ポスターやビラの印刷代も「候補者間でおおむね共通した経費」といえるため、個人的には全く説得的な理由ではないと考えています。
特に公費負担という税金で賄われる可能性がある費用となるため、お金の流れを透明化する観点からは、選挙カーの利用料の収支報告書への記載を不要とする公職選挙法197条2項を削除して、他の公費負担の余地のある費用と同様に、収支報告書に記載する費用とすべきように思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
有権者の方々は、供託金没収ラインに届かないことにより「供託金が返還されないだけ」と思われることが少なくないですが、公費負担で請求できるものも自己負担となるため、自己負担のリスクは、供託金に留まらないことを理解する必要があります。
要するに、現在の公職選挙法における衆議院議員選挙(小選挙区)に立候補するということは、真摯に選挙運動を実施しようとすれば、約515万円を失う経済的リスクを背負って参加する必要があります。
衆議院議員選挙(小選挙区)に立候補するにあたってのこれらの経済的なリスクについて、みなさまはいかがお考えでしょうか。
長くなりましたので、
続きは次回といたします。
~~~【お知らせ】~~~
ラジオに送るハガキやメール
のイメージでお気軽に投稿ください!
ご意見・ご感想お待ちしております!
兼業政治家大すきゆうやの
執務報告書を週末にまとめてお知らせします!
友達登録すれば、応援の注意点もお伝えしています。
毎週火・木の定期的な投稿を予定しています。
政治は日頃から考えることが大事です!
みなさん友達登録お願いします!
ブログの投稿をお知らせする
配信専用のXアカウントです。
みなさまフォローしてご活用お願いします!
<選挙ドットコムからご覧の方へ>
すべての情報は
公式ホームページから発信します!!
是非ともご来訪ください!!
~~~~~~~~~~~~~~~